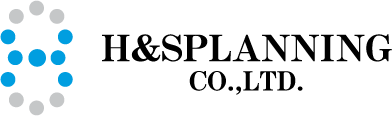福島県の皆さま、こんにちは♪
福島県郡山市を拠点に、県内全域で解体工事を手掛けております H&Sプランニング です😊
今朝、テレビのニュースにて、東京都足立区で老朽化した木造アパートが、
「強制代執行」による解体工事が行われたという話題が報じられていました。
解体にかかった費用はおよそ410万円。
所有者は9回にわたる勧告や指導に応じず、足立区から請求を受ける事態となっています。
このニュースは東京での出来事ですが、「空家特措法」に基づく強制代執行は福島県や郡山市でも十分に起こり得る話です。
実際に、空き家の老朽化や放置は近隣住民の安全・景観に直結し、社会全体の大きな課題となっています。
「実家を相続したけれど、誰も住まないまま空き家になっている」
「解体したいが、費用や手続きが不安でそのままにしている」
こうしたケースは福島県内でも増加しており、決して他人事ではありません。
そこで今回は、空き家を放置した場合のリスクと強制代執行の仕組み、そして事前にできる解体工事の対策について詳しくご紹介いたします。

強制代執行とは?空き家法の流れを解説
全国で深刻化する空き家問題に対応するため、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律に基づき、危険な空き家は行政が段階を踏んで是正を求め、最終的には所有者の意思に関係なく「強制代執行」として解体されることがあります。
「強制代執行」までの流れは以下のように進みます。
- 助言・指導
まずは行政から所有者に対して、管理や修繕について助言・指導が行われます。
ここで改善が行われれば問題ありません。 - 勧告
助言に応じず、倒壊や衛生面で危険があると判断された場合、「特定空家」に指定され、勧告が出されます。
この段階になると、固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が外され、税負担が大きくなる点も注意が必要です。 - 命令
勧告にも従わなければ、解体や修繕を義務付ける「命令」が出されます。
命令違反は50万円以下の過料(罰金)に処されることもあります。 - 代執行(強制解体)
それでも放置されれば、行政が所有者に代わって解体工事を実施します。
この時に発生した費用は、すべて所有者へ請求され、支払い義務が発生します。

今回ニュースで報じられた東京都足立区のケースでは、築46年の木造アパートが約4年間放置され、老朽化が著しい状況にありました。
軒や外壁は崩れ、ベランダも倒壊寸前という危険な状態。
区は繰り返し改善を求めましたが、所有者が応じなかったため、「空き家特措法」に基づき強制代執行を決定。
結果として、約410万円の解体費用を行政が立て替え、後日所有者に請求することとなりました。
つまり空き家の放置は、所有者の事情にかかわらず、
- 解体工事は進められる
- 費用は必ず請求されるという厳しい現実があるのです。
福島県内の空き家事情は?
ここでは福島県内の空き家事情について、具体的な数字で見てみましょう。
2023年度の福島県の空き家数は約 131,000戸、空き家率は15.18%となっています。
空き家率は全国平均の13.84%を上回り、県内での深刻さが浮き彫りになっています。
また、空き家の継続的な増加傾向も見られ、2018年度からは約7,500戸増となっています。
空き家増加の背景には、人口減少や高齢化が影響していると考えられます。

空き家が多い主な地域
福島県内では以下の地域で特に空き家率が高いという結果があります。
- 南相馬市:22.03%
- 会津美里町:20.52%
- 喜多方市:19.91%
- 会津若松市:18.33%
- 白河市:15.98%
- 郡山市:13.95%
城下町として歴史ある地域や、郡山市の農村部にも築年数の古い民家や蔵が残り、
放置されたまま空き家となっているケースが目立ちます。
放置空き家が招く「リスク」
福島県における空き家数は約13万1,000戸、空き家率は15.18%と、全国平均(13.84%)を上回る深刻な状況です。
これは、県内全域において誰にとっても他人事ではない課題であることを示しています。
以下に、放置された空き家が引き起こす具体的なリスクをご紹介します。
1. 倒壊・火災・害虫被害:地域に及ぶリスク
長期間管理されていない空き家は、劣化が加速します。
雨水の浸入による腐食、屋根の崩壊、壁の剥離といった構造的な劣化は、台風や豪雪時などに倒壊リスクを高めます。
放火や火災の発生時には瞬く間に大事故に発展し、近隣にも甚大な被害を及ぼす可能性があります。
2. 犯罪の温床に:放火・不法侵入のリスク
風雨で傷んだ窓や扉は、不法侵入や不審者の滞在を容易にさせます。
近年では、不審者のほかクマなどの動物が住み着く事案も増えており、たびたびニュースで報じられています。
また空き家は放火の対象になりやすく、実際に火元となった事例も少なくありません。
建物自体が「犯罪の起点」になることもあるのです。

3. 税制面の不利益:固定資産税の優遇措置の喪失
空き家対策特別措置法に基づき、行政から「特定空家」の指定を受けると、
従来の「住宅用地に対する固定資産税の軽減措置」が解除され、税負担が大幅に増加します。
所有者には思わぬ税負担が降りかかるリスクもあるため、早めの対応が必要です。
4. 行政による強制代執行:解体費用の請求
法的な勧告や命令に応じない場合、行政は強制的に解体する権限を持ちます。
この「代執行」によって起こる解体費用は、最終的にすべて所有者に請求されます。
所有者がこの解体費用の支払いを拒否した場合、財産差し押さえによって強制的に徴収されます。
差し押さえ対象は現金や預貯金、不動産、株式、貴金属、自動車など、所有者が持つ資産全般に及びます。
安心は「早めの相談・活用」から
空き家のリスクは知っているけど、解体費用が高額で踏み出せないという方が多数だと思います。
費用面の不安を少しでも解消できるポイントを5つご紹介します。
1. 無料見積もりでまずは現状把握
解体費用は建物の構造や広さ、立地条件などによって大きく変わります。
まずは信頼できる業者に現地を見てもらい、解体費用の見積もりを提示してもらいましょう。
具体的な金額が分かると、漠然とした不安が軽減され、計画を立てやすくなります。
福島県内での施工実績がある業者であれば、道路幅や産廃処理費、近隣対応なども含めた現実的な見積もりが可能です。

2. 補助金・助成制度を活用する
郡山市では、空き家解体に対する補助金制度があります。
詳細は過去記事でもご紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。
郡山市空き家解体補助金のご案内
補助金を活用すれば、解体費用の大きな負担を軽減できますので、まずは申請条件や手続きを確認しておくことが大切です。
3. 工事の内容・範囲を調整して費用を分散
解体はすべてを一度に行う必要はありません。
例えば「母屋だけ先に解体して、倉庫は後回しにする」「外構や付帯物は別工事にする」など、段階的に進めることも可能です。
無理なく工事計画を立てることで、初期費用の負担を抑えつつ、状況に応じた柔軟な対応ができます。
4. 将来的な土地活用を見据えて計画する
単に解体費用だけで判断せず、解体後の土地活用を組み合わせると、
収益も含めたトータル視点で資金計画が立てやすくなります。
例えば、
- 駐車場として活用:月極駐車場や一時貸しスペースとして収益化
- 土地を売却し、解体費用に充てる
土地活用まで含めて計画することで、将来的なリスクや費用負担を軽減しやすくなります。
5. 信頼できる業者に相談する
空き家の解体は、単に費用面だけでなく、近隣への配慮や補助金の申請、
解体後の土地活用まで、さまざまなサポートが必要になることがあります。
特に郡山市・福島県内での施工実績がある業者であれば、地域特有の事情や道路環境にも精通しており、
安心して工事を任せることができます。

まとめ|空き家解体は早めの対策が安心につながります
空き家を放置すると、倒壊や火災、害虫被害、放火や不法侵入、税制面での負担、
さらには強制代執行による費用請求など、多くのリスクが待ち受けています。
特に福島県や郡山市でも空き家は増加傾向にあり、建物を所有している方にとっては決して他人事ではありません。
一方で、解体工事は費用や手続きが心配という方も多いかと思います。
しかし、信頼できる業者に相談し、補助金の活用や工事計画を早めに行うことで、
負担を抑えながら安全に解体を進めることが可能です。
空き家の放置リスクを未然に防ぎ、未来の負担を軽減するためにも、
まずは現状の把握と信頼できる業者への相談から始めましょう。
郡山市で空き家解体をご検討の方は、ぜひお気軽にH&Sプランニングまでご相談ください。
補助金のサポートやその後の土地活用まで、ワンストップでサポートいたします。
福島県で解体工事をご検討中の方は、ぜひ一度お問合せ下さい♪
お問い合わせは下記からどうぞ(^^)
【解体工事×H&Sプランニング】
▶ホームページ
▶解体工事のご相談・お見積りはこちらから
▶Instagram
【内装解体×内装リセットPRO】
▶内装解体工事のご相談・お見積りはこちらから
【エクステリア×ALIVIO】
▶エクステリア工事のご相談・お見積りはこちらから
▶Instagram