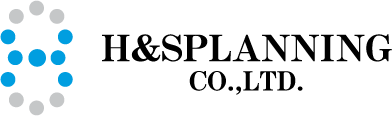福島県のみなさんこんにちは♪
H&Sプランニングのホームページをご覧いただきありがとうございます!
福島県郡山市を拠点に福島県内全域を対象に解体工事を行っているH&Sプランニングです☆
こちらのお知らせでは、解体工事に関する情報や豆知識、
福島県の解体工事に関する補助金についてのブログなどをアップしています。
福島県のみなさんのお役に立てれば嬉しいです☆
さて!いつも工事についてや現場についての記事が多いため、
本日は、解体工事の事務手続きに関することをご紹介したいと思います。
建物を解体したら、「解体証明書」という書類が必要になります。
解体工事を行う機会は人生の中でほとんどない方が多いため、
この証明書について初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。
本日は、「解体証明書」とそれに関係する「建物滅失登記」についてご紹介します。
今後解体工事を検討されている方にとっては、お役に立つ情報だと思いますのでぜひ最後までご覧ください(^^)

解体証明書とは
「解体証明書」とは、「建物滅失証明書」「建物取り壊し証明書」とも呼ばれ、
建物の解体が完了した時に、解体業者が作成する書類のことを言います。
解体証明書は、あとにご紹介する建物滅失登記を行う際にも必要となる重要な書類です。。
解体証明書は誰が発行する?
先ほども触れましたが、「解体証明書」は解体工事を実施した解体業者が発行します。
この証明書は、解体工事が確実に完了したことを証明する重要な書類であり、解体業者が実印を捺印して作成します。
この「解体証明書」は、解体工事後に行う【滅失登記】の手続きにおいて必須となる大切な書類です。
滅失登記とは、建物が取り壊されたことを法務局に届け出る手続きであり、
不動産登記簿からその建物を抹消するために必要なものです。
そのため、工事が完了した際には、速やかに解体業者に証明書の発行を依頼しましょう。

解体証明書は自分で作成可能
解体証明書は、自分で作成することも可能です。
法務局のホームページには作成例が掲載されており、その例に従って書類を作成し、
解体業者から捺印と署名をもらえば完成します。
この方法を利用すれば、解体証明書を自分で準備することができます。
しかし、書類作成は慣れていない方にとって手間がかかる場合があります。
特に、お勤めをしている方やご高齢の方にとっては、大きな負担になることも考えられます。
そのため、解体業者に書類の作成を依頼する方が効率的です。
解体業者は解体証明書の作成に慣れており、内容の不備が発生しにくい点も大きなメリットです。
滅失登記とは
滅失登記は、建物が解体や火災などで物理的に存在しなくなった場合に、
その事実を不動産登記簿に反映させるための手続きです。
不動産登記法第57条に基づき、建物の滅失日から1か月以内に申請する義務があります。
滅失登記の目的
滅失登記の目的は、建物が存在しない状態を法的に記録することで、不動産登記簿を正確に保つことです。
また、新しい建物を建てる際や土地の売却時に必要な手続きとなるため、重要な役割を果たします。
滅失登記の罰則
不動産登記法第164条により、滅失登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、「正当な理由」がある場合には過料が免除されることもあります
過料以外のデメリットとは
滅失登記を忘れてしまったり、何らかの理由で手続きを済ませていない場合、
実際には建物が取り壊されていても、登記簿上では建物が存在している状態が続きます。
この状況では、固定資産税が課される可能性があります。
固定資産税は土地に固着した建物に対して課税されるため、
滅失登記を行わないと、本来払う必要のない税金を支払うことになる恐れがあります。
さらに、土地の売却を考えている場合にも問題が生じます。
登記簿上では建物が存在している状態となるため、買い手に不信感を与えたり、
売却手続きが複雑化することで売却の機会を逃してしまう可能性があります。
特に、住宅ローンの利用が困難になるなど、金融機関からの融資が受けられなくなるケースも考えられます。
このようなリスクを避けるためにも、解体工事が完了したら速やかに滅失登記を行うことが重要です。
手続きを怠ることで発生する不必要な税金や売却機会の損失を防ぐためにも、期限内に確実に申請を済ませましょう。
解体工事前に確認しておきたいこと
建物の解体工事を行う際に、書類上複雑になることの無いよう
事前に確認しておいた方が良い点が2つあります。
以下にまとめましたので、一つずつ見て行きましょう^^
住宅ローンの有無
住宅の解体工事を行う理由は人それぞれですが、
住宅ローンの返済が残っている場合には特に注意が必要です。
住宅ローンの返済期間は通常25年から30年と長期間にわたるため、
その期間中に解体工事を行う際には、ローンを組んだ銀行の許可を得る必要があります。
これは、建物が解体されることで銀行が抵当権や所有権を失うことを防ぐためです。
もし許可を得ずに建物を取り壊してしまうと、銀行との間でトラブルが発生する可能性があります。
銀行は抵当権を担保として融資を行っているため、建物が無くなれば担保価値が失われることになります。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、住宅ローンの状況や抵当権の有無についてしっかり確認し、
銀行との連携を図りながら計画的に解体工事を進めましょう。

建物の所有権を確認する
解体予定の建物が亡くなったご両親から相続したものである場合、
所有権がご両親の名義のままになっていることがよくあります。
このような場合には、滅失登記をスムーズに進めるため、
所有者の親族であることを証明する書類を準備しておくことが重要です。
具体的には、戸籍謄本を取得しておくと安心です。
戸籍謄本があれば、法務局での手続き時に所有者との関係を証明することができ、申請が円滑に進みます。
また、相続人であることを証明するための除籍謄本や住民票の除票なども必要になるケースがあります。
解体工事を計画する際には、事前にこれらの書類を準備し、法務局での滅失登記手続きに備えることをおすすめします。
建物滅失登記の流れ
ここでは、滅失登記に必要な書類や流れについてご紹介します。
必要書類
滅失登記の申請に必要な書類は以下の通りです。
⑴滅失登記申請書
⑵解体証明書
⑶解体業者の印鑑証明
⑷解体業者の会社謄本OR資格証明
⑸住宅地図
⑵・⑶・⑷は、工事終了後に解体業者が準備してくれます。
⑸の住宅地図は、建物があった場所に目印を付けて提出します。
後日、法務局職員が地図を元に現地の確認を行います。
⑴の滅失登記申請書については、法務局のHPよりダウンロードできます。
記載例も準備されていますので、その通り記入します。
↓福島地方法務局のHPは以下となります↓
> 申請書ダウンロードはこちらから
この時、法務局で登記簿謄本を取得してあると問題なく埋めることができます。
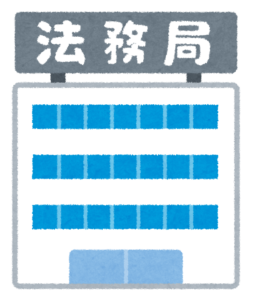
申請の流れ
1.法務局で建物の登記簿謄本を取得する
2.取得した登記簿謄本を元に、滅失登記申請書を作成する
3.解体業者から解体証明書等の必要書類が届く
4.必要書類を添付し、登記の申請を行う。
5.登記完了後、登記完了証を受け取る。
登記の申請が困難な場合は、土地家屋調査士に依頼することも可能です。
その際には、委任状が必要になります。
なお、登記に関する手続きは司法書士が思い浮かびますが、
滅失登記に関しては、司法書士への依頼はできませんので注意しましょう!
最後に ~福島県の皆さまへ~
本日は、解体工事後に重要な「解体証明書」と「滅失登記」についてご紹介しました。
滅失登記は、解体された建物が正式に登記簿から抹消されるために欠かせない手続きで、法律で義務付けられています。
申請期限は解体日から1か月以内と定められており、これを過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があるほか、
固定資産税が不要な建物に課税され続けるリスク、土地売却や新築計画に支障をきたす恐れがあります。
1か月という期間は一見長く感じられるかもしれませんが、日々の忙しさの中で意外とあっという間に過ぎてしまうものです。
そのため、解体工事を計画する段階から必要書類の準備やスケジュール調整を進めておくことが大切です。
専門家への相談や早めの書類準備が、スムーズな手続きへの近道となるでしょう。
弊社では、解体工事はもちろん、これに伴う各種手続きについても丁寧にサポートいたします。
解体工事をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
> ご相談・お見積りはこちらから
Instagramもご覧ください♪
> インスタはこちらから☆